展示
過去の企画展・特別展一覧
ミニ展示「博物館収蔵資料展~源寿院(げんじゅいん)の和時計など」

江戸時代に作られた9点の和時計を展示しました。江戸時代の大名や豪商たちが使用したもので、日本独特の不定時法と呼ばれる時刻制度にのっとった時計です。 一部の時計は、展示期間終了後も館内に常設展示しています。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成26年4月5日(土曜日)から4月13日(日曜日)
詳細情報を見る葛探写真館「かつしか昭和の風景 PART 8」

葛飾探検団が収集した昭和期の葛飾の風景や暮らしぶりを物語る写真を展示します。写真に記録された「かつしかの昭和の風景」をお楽しみください。 会場:郷土と天文の博物館 特別企画展示室 会期:平成27年3月15日(日曜日)~5月17日(日曜日)
詳細情報を見るかつしか郷土かるた原画展

世界的な切り絵画家の辰己雅章氏による、「かつしか郷土かるた」の原画を展示します。 「かつしか郷土かるた」は、「葛飾に住む誰もが、いつまでもふるさとに誇りを持ち、愛し続けて欲しい」という願いから誕生しました。 かるたに詠まれている44の題材は、区内の小・中学生から寄せられた5,379句の読み札の「ことば」をもとに、制作しました。切り絵で描かれた葛飾の歴史や自然などをお楽しみください。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成26年12月2日(火曜日)~平成27年2月28日(土曜日)
詳細情報を見る特別展「葛飾探検団 かつしか街歩きアーカイブス Part2」

博物館ボランティア「葛飾探検団」は、葛飾の暮らしや文化、そしてまちの風景が時代の移り変わりとともに、どのように変化したかを調査研究しています。 本展示は、活動15年間の調査成果を基に、「銭湯」、「路地」、「煙突」、「商売の風景」「水の記憶」等に注目し、葛飾のまちの移り変わりや失われた風景、あるいは失われつつある風景について展示解説します。 平成21年度に現代に残る葛飾の昭和レトロを紹介して好評を得た「かつしか街歩きアーカイブス」の第二弾です。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成26年7月27日(日曜日)から9月15日(月曜日・祝日)
詳細情報を見る企画展「日本刀の美と技 葛飾の名工たち」

日本刀は反りのある刀です。この独特な形は平安時代に成立したと考えられます。素材の玉鋼を鍛錬して作り上げ、武器としての機能を高めました。また、刃文や地金などの装飾性も追求されてきました。 葛飾区内には、東京都指定無形文化財保持者、葛飾区無形文化財保持者である日本刀製作技術に関わる刀鍛冶、研師、白銀師の職人が6人います。現代の日本刀は、これら葛飾区在住の職人たちを含む多くの職人による伝統技術が維持されることによって製作されています。 日本刀の製作には、多くの職人が携わり、多くの工程を必要とします。この展示では、日本刀の製作過程、職人の持つ技術を紹介し、葛飾区在住の日本刀製作に関わる職人の優れた作品を展示します。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成26年4月26日(土曜日)から6月15日(日曜日)
詳細情報を見る特別展「肥やしの底チカラ」

江戸時代、世界最大の都市といわれていた江戸。葛飾区は周辺の農村の一つとして発展してきました。江戸周辺の農村の役割の一つは、町に住む人たちに野菜などの食糧を供給すること、そして町の生活廃棄物を「肥やし」という形で使い、環境を衛生的に保つことでした。 葛飾区が下肥を利用し、質の高い野菜を生産して町の人たちに還元してきた歴史や、江戸・東京と近郊の農村の間の下肥を通じた交流を明らかにします。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成25年8月4日(日曜日)から9月16日(月曜日・祝日)
詳細情報を見るかつしか郷土かるた原画展

世界的な切り絵画家の辰己雅章氏による、かるたの原画と作品の展示を行います。 「かつしか郷土かるた」は、「葛飾に住む誰もが、いつまでもふるさとに誇りを持ち、愛し続けて欲しい」との願いから生れました。 かるたに取り上げた44の題材は、小・中学生から寄せられた5,379句の読み札の「ことば」をもとに、自然、産業、文化・歴史、人物などを選定し地域性も考慮して作成しました。 この展示では、辰己雅章氏による44点の絵札の原画のほか、30点以上の作品も一挙に公開。 かるたの絵札では十分に味わうことのできない原画の素晴らしさと、辰己雅章氏の多彩な魅力を是非ご堪能ください。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成24年12月15日(土曜日)~平成25年2月3日(日曜日)
詳細情報を見る区制施行80周年記念特別展「東京低地災害史」
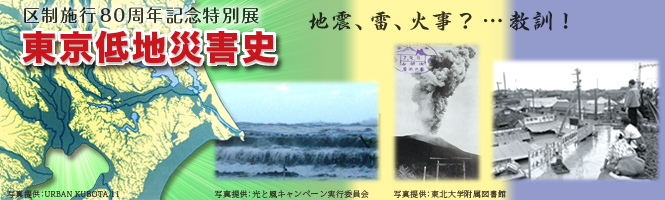
2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災は、自然と人間の関わり方を根底からくつがえす出来事でした。 1年半余を経過した今も、被災地の復興は進まず、多くの方々が自宅に帰れない、以前の仕事に就くことができない等、苦しい状態が続いています。 特に、福島第一原発は、廃炉まで何十年もの時間が必要とされ、周辺の帰宅困難及び居住制限区域の方々が、以前の生活を取り戻すには、多くの困難が予想されます。 この展示では17世紀以降、東京低地が立地する関東平野における歴史災害の検証を試みました。多くの災害は避けては通れないものですが、先人は、自然と共生しながらも、発生した諸災害と立ち向かい、復興をとげてきました。 残された史料から、災害の教訓を少しでも未来に継承し、改めて自然と向かい合う契機になれば幸いです。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成24年10月7日~11月25日
詳細情報を見る区制施行80周年記念企画展「葛飾区80年 町・暮らしの移り変わり」
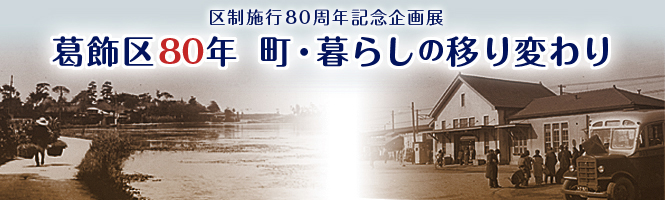
葛飾区は昭和7年(1932)、それまでの東京府南葛飾郡下の七か町村がひとつになって誕生した自治体です。 当時、まだ農村の景観が残っており、人口は84,726人に過ぎませんでした。 この企画展は、区制施行80周年という節目に当たって、都市近郊農村であった葛飾区が、どのように都市化してきたのかを振り返り、そのようすを物語る写真やゆかりの資料を紹介していくものです。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成24年7月28日~9月9日
詳細情報を見る区制施行80周年記念企画展「平櫛田中とかつしか」
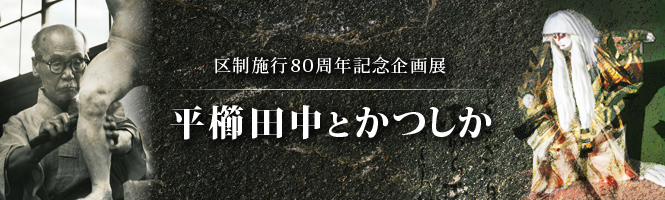
近代彫刻の巨匠、平櫛田中。平櫛田中は、昭和14年(1939)に葛飾区のお花茶屋駅に程近い本田宝木塚町にアトリエを構え、幾多の名作を生みだしました。 東京国立劇場のロビーに展示されている「鏡獅子」の大像は、代表作であり、日本の近代木彫の最高傑作と多くの方から称賛されています。 本展では、20点余りの多彩な彫刻作品をはじめ、書や手紙、写真などを展示し、田中芸術と田中の人となりや葛飾区にあったアトリエの様子なども紹介いたします。 会場:郷土と天文の博物館 会期:平成24年5月26日~6月17日
詳細情報を見る